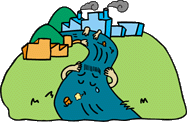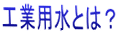
工場で使われる水は「工業用水(こうぎょうようすい)」とよばれています。
工業用水はせいぞうする品物(しなもの)に水を使うもの、せいぞうするとちゅうで洗う作業に使うもの、温度や湿度(しつど)を調節(ちょうせつ)することに使うものなどがあります。そして、使い終わった水は薬品や重金属(じゅうきんぞく)などでよごれていることが多いのです。

日本全国で、工場がつぎつぎにけんせつされた1960年代には、工場からだされる排水(はいすい)の多くはきたないまま川に放流(ほうりゅう)されていました。ところが、化学工場の排水にふくまれていた重金属が原因で、水俣病(みなまたびょう)などさまざまな公害病がおこることが明らかになりました。
また、製紙工場(せいしこうじょう)からの排水で駿河湾(するがわん)がヘドロでうまるなどの事件がおきて、工場排水のよごれが大きな社会問題になりました。 |
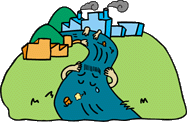 |
このようなことをきっかけに、工場の排水について国の基準(きじゅん)がきびしくなり、工場でも排水をきれいにしようという考えかたがひろまりました。大きな工場では、排水をきれいにして川にもどすせつびをととのえるようになりました。

1980年代になると、工業用水は使う量がふえなくなりました。その理由は、多くの工場で使ったあとの排水をきれいにして、くりかえして何回も使えるせつびをそなえる工場がふえてきたからです。大切な水を工場の中でくりかえし使うリサイクルぎじゅつが進んだからです。
大きな工場では、1970年ころは生産せつびからでる排水の約50パーセントをきれいにして、ふたたび使うリサイクル水としていましたが、1990年ころになると、リサイクルのひりつは75パーセントにまで高まりました。使い終わった薬品をあつめて、ふたたび使うこともおこなわれるようになっています。
|
 |
|