|
松くい虫のひがい |
|---|
| 松(まつ)の木は、わたしたち日本人にとって、なじみのある木です。 その松が、松くい虫によって、ひがいをうけています。 松くい虫というのは、マツノザイセンチュウという線虫です。 マツノザイセンチュウは、北アメリカから入ってきた生物で、形はミミズのようですが、長さが1ミリメートルくらいのとても小さな生物です。松の幹(みき)の中で、水のとおりみちをふさいでしまうため、松の葉(は)がきゅうに赤くなって枯(か)れてしまいます。 このマツノザイセンチュウを、マツノマダラカミキリ(カミキリムシの1種)という虫が、次々にべつの松の木へはこぶため、松枯れのひがいが広がります。
三重県での松くい虫による松枯れは、昭和51(1976)年からふえはじめ、昭和56(1981)年にピークをむかえました。その後はだんだんひがいがへり、平成14(2002)年にはピークのときのおよそ12%にまでへりました。 しかし、ここ数年は、雨が少なくて気おんが高い日が多く、松枯れのひがいがしんぱいされます。 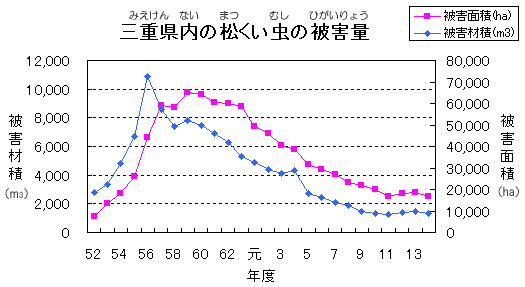 とくに、海岸(かいがん)ぞいの木は、雨や気おんのえいきょうをうけやすく、松枯れのよぼうや、松くい虫のくじょ(薬をまいたり、松くい虫のたまごがある木をとりのぞいたりすること。)をおこなっても、まだひがいがふえています。
これからまい年、雨が少なかったり、気おんが高かったりする天気がつづくわけではありませんが、少しでも松枯れのひがいがおさまってほしいものです。 |




