| 里山(さとやま)とはどんなところ? |
|---|
 伝統的(でんとうてきな)な里山のようす 伝統的(でんとうてきな)な里山のようす
江戸時代のなかばから1960年代ころまでの里山は、人びとが生活や農業を行なううえで必要な水田、畑、水路、ため池、草地、かや場、森林などがしゅうらくのまわりにまとまって分布していました。 |
 里山の風景(ふうけい) |
|
人びとは水田や畑でお米や野菜などの食料をつくり、かや場から屋根にふく「かや」を集めていました。薪炭林(しんたんりん)とよばれる森林からは、薪(まき)や柴(しば)、炭(すみ)となるクヌギ、コナラなどを定期的(ていきてき)に切っていました。
森林からは、家を建てるときには木材として利用するアカマツやスギなども切り出されていました。 水田や畑のひりょう、あるいは牛や馬のえさとして使う草木や落ち葉は、草地や森林の中でとっていました。 |
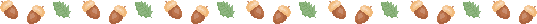 |
 里山の自然と文化 里山の自然と文化
里山でみられた土地の利用のしかたは、集落(しゅうらく)で決めたやくそくや人びとの経験(けいけん)にもとづいて、切りすぎたり、災害(さいがい)を引き起こしたりしないように注意ぶかくおこなわれました。そして、地域(ちいき)にある草木などの資源(しげん)を、自分たちだけでなく何世代(なんせだい)にもわたって利用できるように工夫した方法がとられ、地域の知恵(ちえ)や技術(ぎじゅつ)として伝わってきました。
里山には、水田の水の手入れ、森林の定期的な伐採(ばっさい)などの人びとの営み(いとなみ)に応じたさまざまな生き物が生息(せいそく)してきました。
|
 1970年以降の里山 1970年以降の里山
1970年代になると、化学肥料(かがくひりょう)やプロパンガスの普及(ふきゅう)などにより、薪炭林、草地、かや場は利用されなくなりました。 人びとの生活との結びつきがうすれた里山は放置(ほうち)されたり、宅地開発(たくちかいはつ)がおこなわれて大きくすがたを変えました。
|

出典:森と木の質問箱/日本林業技術協会(2002年)

 また、伐採や草刈など必要な手入れがおこなわれず、日当たりや刈りこまれた場所を好む生物が森林からすがたを消したり、ゴミがすてられるなど、多くの問題をかかえるようになりました。
また、伐採や草刈など必要な手入れがおこなわれず、日当たりや刈りこまれた場所を好む生物が森林からすがたを消したり、ゴミがすてられるなど、多くの問題をかかえるようになりました。