スタッフブログ
環境基礎講座2025第1回「地球温暖化」報告
*************************************************************************************
【日時】令和7年6月14日(土) 13:45~16:30
【場所】三重県総合文化センター
【演題と講師】
第1講
「脱炭素社会の実現に向けた取組」
伊藤 瑞紀 氏(三重県環境生活部環境共生局地球温暖化対策課)
第2講
「三重県における気候変動の影響と適応策」
樋口 俊実 氏(元三重県気候変動適応センター事務局長)
【参加人数】第1講 51人 第2講 51人
*************************************************************************************
第1講は、三重県地球温暖化対策課の伊藤さんより、地球温暖化とは何か、地球温暖化の現状と将来予測、国や三重県の取り組みについて説明がありました。三重県の温室効果ガス排出量は全国に比べて高いのが現状で、産業部門の多いのが要因かもしれないとのことでした。また今年2月18日に国で閣議決定された地球温暖化対策計画について触れられ、2050年にCO2ネットゼロを目指すため、2035年には60%削減、2040年には73%削減を新たに目指していくことを説明されました。また環境省の「脱炭素先行地域」では、2024年9月に三重県内としては初めて、度会町・多気町・明和町・大台町・大紀町・紀北町の6町の取組が選ばれています。

最後に、地球温暖化対策でわたしたちにできることとして、「みえデコ活」について説明され、脱炭素型ライフスタイルへの転換として①省エネ家電購入応援キャンペーン、②太陽光発電設備などの設置費補助金や共同購入事業、③住宅省エネキャンペーン、④電気自動車等導入補助金についてご紹介いただきました。
第2講では、元三重県気候変動適応センター事務局長の樋口さんより、地球温暖化の現状と将来予測について詳しく説明していただきました。過去100年あたりで日本の気温は1.4℃上昇しており、IPCC第6次評価報告書における気温や海面水位の様々な将来予測を説明され、気温は下降に転じたとしても海面上昇は続いてしまうという厳しい状況を伝えられました。三重県でも気温は上昇しており、真夏日・猛暑日は増加、年間の降水量は減ってはいるが豪雨やドカ雪は増える傾向にあり、災害につながりやすい危険な状況をお話しされました。

そして、地球温暖化対策としてその影響に備え、被害を軽減するための「適応」策について様々な具体例をお話いただきました。高温にも強いお米「結びの神」やイチゴ「かおり野」、高い水温でも育つ黒ノリ「みえのあかり」の開発などです。また、海で起きている変化として、黒潮大蛇行やレジームシフト(大規模な魚種の交代)についても触れられました。熱中症対策として学校のプールにおけるWBGT測定装置の導入やクーリングシェルターの指定、治水プロジェクトとしての田んぼダム、浸水を想定しハザードマップを見ておく重要性なども述べられました。
樋口さんは、「適応」策は万能ではなく、さまざまな限界があり、もっとも重要なのは、地球温暖化の原因である温室効果ガスを削減する「緩和」策に私たちが取り組むことである、と最後に強調されました。
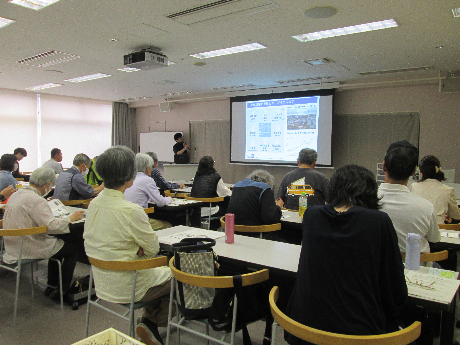
質疑応答では、カーボンプライシングによる緩和策をどう考えるか?住宅に太陽光発電を付けて本当にペイできるのか?など、地球温暖化対策に関する疑問や意見が述べられました。この講座をきっかけに参加者の方々がよりさらに地球温暖化防止について考えを深め、取り組んでいただけたらと願います。
【報告:大山】
